アーカスプロジェクト ディレクター
アーカスプロジェクトとは

もりや学びの里
アーカスプロジェクト(以下、アーカス)は、茨城県と守谷市などで組織された実行委員会が運営母体となり、茨城県守谷市の廃校を活用した生涯学習施設「もりや学びの里」内のアーカススタジオで展開している芸術文化事業である。アーティストの滞在制作支援などのプログラムを行なうアーティスト・イン・レジデンス事業(以下、AIR)がその主軸を成しており、1994年のプレ事業開始から数えると2022年度で29年目に入る、我が国においては先駆け的なAIRである。この短い報告では、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の流行によって、アーカスのAIRがどのような影響を受けたのかについて現場の声を届けたい。
平時のアーカス
コロナの世界的流行がAIRに与えた影響について述べる前に、通常の年間プログラムの構成について伝えておきたい。それは、大きく2本の柱によって構成されている。一つは、国内外のアーティストの滞在制作を支援したり交流を促したりする「アーティスト・イン・レジデンスプログラム」だ。そこには、アーカスの顔とも言える公募によるAIR(以下、公募AIR)*がある。もう一つは、市民に向けてワークショップや講座などを行う「地域プログラム」でだ。これは地域におけるアート活動の意義を検証するとともに、子どもから大人まで幅広い年代の人々の創造的な可能性を探究する取り組みである。公募AIRでは、春先に国内外のアーティストを対象に公募を行い、5月の審査会で海外のアーティストを2組、国内のアーティストを1組選出する。アーティストは9月上旬からアーカスでの滞在制作をはじめ、11月下旬の「オープンスタジオ」での成果発表を経て、12月上旬にプログラムを終了する。
上記の年間プログラムと並行して、中長期的な取り組みがある。それは、アーカスの財政的な基盤の整備とそのためのプログラムの見直しや開発、そして運営体制を見極めることである。公募AIRにおける申請料の導入、アーティストに限らないレジデンスプログラムの策定、さらには他団体や地方自治体とのAIRの共同運営などを企画し、実行に移している。
コロナの流行と公募AIRにおける変更と調整
こうした業務があるところにコロナの波がやってきたわけだが、ここでは、そのなかでもプログラムの計画と内容の絶えざる変更と調整を迫られた公募AIRについて時系列的に振り返ってみたい。
2020年4月。年度がはじまってすぐに一回目の緊急事態宣言が出た。コロナに関する状況がつかめず先行きが不透明ながらも、アーティストの募集と審査を進め、6月上旬には、ラトビア出身でロサンゼルス在住のイエヴァ・ラウドゥセパ、アルバニア出身のクローディアナ・ミロナと台湾出身のユァン・チュン・リウによるデュオでロッテルダム在住のミロナリウ、そして東京を拠点とする6人組のアーティスト・コレクティブ、オル太を選出した。この時点で、国境ばかりか県境をまたいだ往来も制限されていたため、例年のスケジュールに沿ってプログラムを実施することが叶わないことは認識していた。そして、アーティストの査証の手続きなどの業務には入らず、7月には、海外のラウドゥセパとミロナリウはオンラインで、またオル太は、時期を見て守谷に通いながらAIRを行うこと、加えて2021年度には3組とも改めて守谷に招聘して滞在制作と成果発表を行うことを決めた。そのため、2020年度は、それぞれ調査対象について文献を当たったり、専門家へ聞き取りをしたりして作品制作の準備を進め、実制作に入るまでの作業を進めることとした。作業の進捗は、オンラインでのチュートリアルをとおして図った。ラウドゥセパは、ソヴィエト連邦の映画監督アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972年)に出てくる、未来の表象としての首都高についてリサーチを進め、ミロナリウは、大日本帝国時代に台湾で品種改良されたジャポニカ米である蓬萊米(ほうらいまい)をとおして育種や土地改良をめぐる統治のあり方を考察した。そして、オル太は、守谷市内において不耕起栽培を実践するために遊休地を探し、また有機農業を実践している農家への聞き取りをした。

イエヴァ・ラウドゥセパによる、建築史家 五十嵐太郎氏へのインタビュー
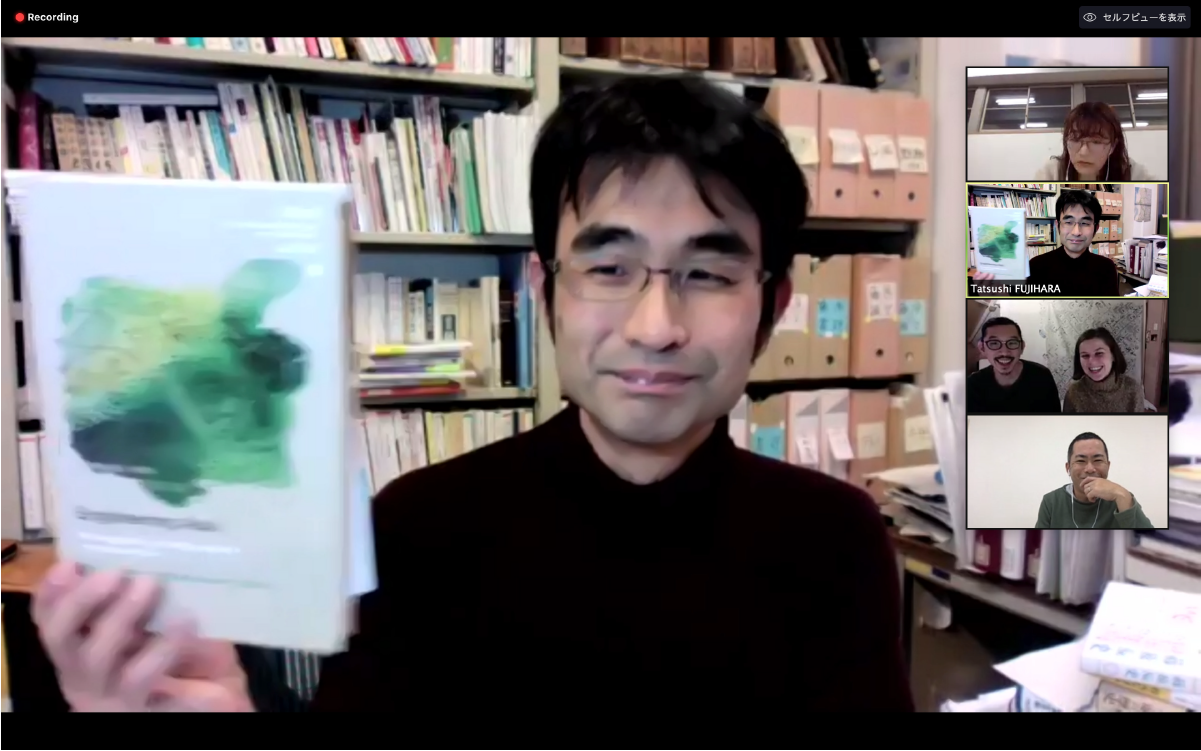
ミロナリウによる、歴史学者 藤原辰史氏へのインタビュー

守谷における、オル太と宮崎毅氏(環境地水学)によるプロジェクト候補地の視察
3組のアーティストとアーカスの活動は、双方にとってはじめての試みで、たどたどしく進んだが、終盤にはある事柄を除いて想定していたところまでは到達できていた。ある事柄。それは、アーティスト同士が同じ土地で同じ時間を過ごすことによって可能になる知識や技術の交換、そして連帯意識の醸成である。食材の調達や訪れた展覧会、また経験した他のAIRなどについての些細なやり取りの積み重ねで、守谷という地域への帰属意識が生まれたり相互の作品や活動への理解が深まったりする。こうして生まれるアーティスト間の協調関係がAIRの推進力となり、またはじめての場所において活動するアーティストの心身を健康に保つのだ。例年と比べると、それがすっぽりと抜け落ちていた。オンラインを使えばそれも実現できるように思えるが、標準時が大きく異なる3地点を結ぶこと自体が困難であったことも付け加えておく。ともあれ、初年度の締めくくりとして、途中経過の報告会をオンラインで行い、ライブ配信を行なった。
公募AIR2年目、計画の変更とプログラムのまとめ
2021年度に入り、公募AIRは次のような方針で進めることにした。ラウドゥセパやミロナリウ、オル太とともに、2021年度の公募によって海外の申請者から選ばれたアーティスト1名が、9月から12月までアーカススタジオにて滞在制作を行い、成果を発表することとする。しかしながら、渡航時期の判断に猶予を持たせつつ来日時の隔離など現実的な課題を踏まえ、例年設定している100日間ではなく85日間とした。2021年度の招聘アーティストとして233名の応募者から選ばれたのは、マーストリヒト在住のマリョライン・ファン・デル・ローであった。
いったんは、この方針に従って進めていたものの、コロナの第4波と第5波で、4月中旬から9月下旬までまん延防止等重点措置と緊急事態宣言が交互に発令されたのを受け、アーカスとしては、渡航制限の解除を心待ちにしながら最終的な方針決定を可能な限り遅らせた。しかし状況の好転は見込めなかったため、結局9月上旬に、前年度につづいてオンラインによるAIRを実施することに決めた。この判断に伴い、プログラム期間を12月上旬から2022年2月下旬までに変更し、2020年度から参加している3組のアーティストに関しては、2月中旬のオープンスタジオで成果を発表し、プログラムを終了することにした。区切りをつけることによってアーカスへの参加を実績にし、別の機会に来日して作品を完成するための足掛かりとするためだ。そして、ファン・デル・ローは、2021年度はオンラインで、テーマである妖怪「桂男」と桂の木についてリサーチを進め、2022年度に実地でAIRを行うこととした。
ラウドゥセパとミロナリウは来日することなくプログラムを終えることをとても残念がっていたが、この後にやってくるオミクロン株の流行による第6波を今考えれば、この判断は間違ってはいなかったと思う。そして、最終的に、ラウドゥセパは、タルコフスキーが『惑星ソラリス』の制作時にソビエト連邦当局から日本への渡航許可が下りなかったというエピソードを自分の身の上と重ね合わせて作品の構想を練り上げ、シングルスクリーンの映像作品を作った。ラトビアの首都リガの高速道路の車窓を取り入れながら、『惑星ソラリス』で描かれた未来を想起させつつ、コロナに翻弄される現代から見える先行き不透明な未来を想像させた。ミロナリウは、展示の指示書をアーカスに送り、2面のスクリーンに同期した映像を投影した。そして、「蓬萊」という理想郷のイメージの背後で抜き差しがたく結びついた大日本帝国と台湾の関係を資料性の高い映像や文献を駆使しながら紐解いた。オル太は、市民から借り受けた不耕作地において、陸稲や瓜、豆類などの種を蒔いて不耕起栽培で育て、収穫するとともに、建築申請をしてオル太のメンバーが滞在する小屋を耕作地内に建てた。またスタジオには、収穫物のみならず収穫物の木版リトグラフや粘土で作ったオブジェなどを展示した。

オンラインオープンスタジオ用のインスタレーションビュー
イエヴァ・ラウドゥセパ《Tokyo Highway Scene》

オル太《耕す家》活動風景

オル太《耕す家》活動風景
何とコロナの第6波は、オープンスタジオにも影響を与えた。当初は例年どおり鑑賞者を迎え入れて公開する予定であった。しかしながら、12月に入った時点で、年末年始にかけてのコロナ感染者増と緊急事態宣言の発令を想定し、オンサイト(アーカススタジオに鑑賞者を迎え入れて実施)とオンラインを併せて行うという方針を立てた。その後、2022年の1月に入って東京都や近県にまん延防止等重点措置が敷かれたため、結局オンサイトは取りやめにしてオンラインのみで行うことにした。その決定後、特設ウェブサイトの作成と作品の展示を並行して行い、最終的に3月上旬に、作品の展示の様子や映像作品また収録したアーティストトークなどを公開した。

オンラインオープンスタジオ用のアーティストトーク収録風景
ミロナリウ
コロナ禍のなかでのAIRの可能性
こうして見ると、通常のAIRの可能性に向けて調整を重ねてきたものの、その大部分がオンラインに拠ったプログラムへの変更や調整を余儀なくされたことがわかる。このためにアーティストもアーカスもなかなか制作に集中することができなかったが、最後には双方とも協力し合いながら創意工夫を凝らして作品を設営して成果を形にし、公開へと漕ぎ着けたことは、コロナ禍のなかにおける限られたAIRの可能性を最大限に追い求めた結果であると述べておきたい。一方で、別のAIRプログラムでは、移動が叶わなくとも国境を超えたアーティストの交流を実験的に探ったことも書き留めておく。それは、ソウル市美術館が行っているセマ・ナンジレジデンシーとアーカスの共同プロジェクトで、オンライン上にプラットフォームを作成し、韓国やドイツ、日本のアーティスト6名がそのプラットフォーム上で共同制作を行うというものである。アーカス側からは、彫刻家の井田大介が参加した。移動を前提として成立しているように思えるAIRだが、創作環境の設計によっては移動せずともアーティストの交流や協働は可能になる。ただし、作品を共同で制作する上で、アーティストたちが直接会わないことが必要十分条件であるかどうかは、今後さまざまな類似プログラムが出てくるなかで検証されなければならないだろう。
2022年度へ
アーカスは、コロナとともにある世界において、3度目の春を迎えようとしている。2022年度の公募AIRでは、新たに海外から1組、国内から1組を選出し、ファン・デル・ローとともに3組を受け入れる予定でプログラムを構築しているところだ。また、それ以外にも、新たに計画したレジデンスプログラムや市民を対象としたワークショップや講座、そして他の地方自治体とのAIRの共同運営が実現に向けて進んでいる。コロナの波は引いてはまた寄せてくるであろうが、柔軟な組織運営とプログラム、またスタッフで応じてゆこうと日々確認しているところである。
アーカスプロジェクト ディレクター


