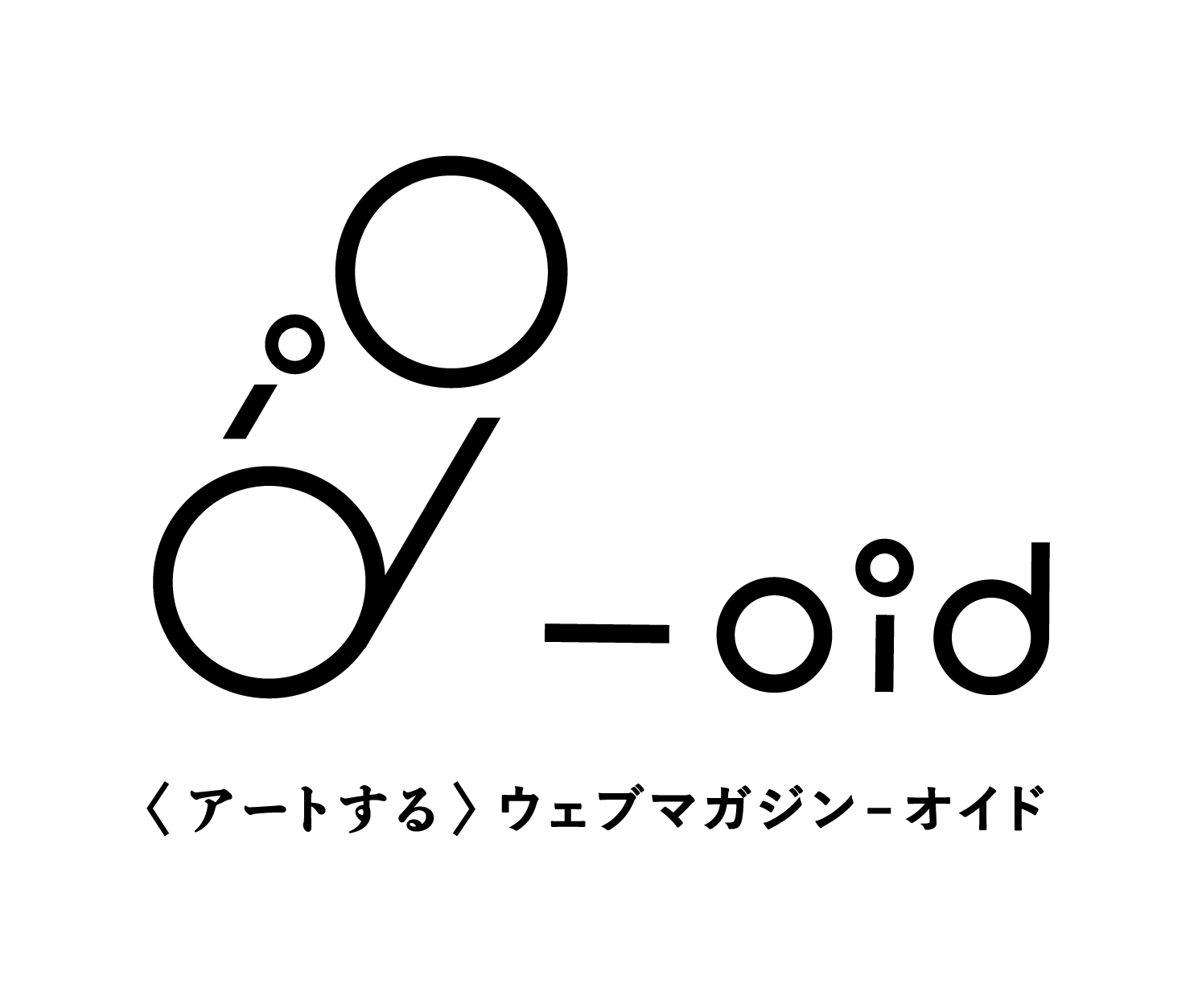「マンガにかかわる」を再考する
大津留香織
このたび、ウェブマガジン “-oid” の特集テーマを「マンガ」とし、関係する人々のインタビューやレポート記事、評論などをお届けすることになった。サブカルチャーであったマンガはアニメを通して世界に輸出され、今や日本の最も重要な文化産業であると捉えて差し支えない。いまだにハイカルチャーではないと把握されながら、大学における関連学科の設置、行政とのコラボレーション、専門博物館の開館など、マンガに関する動きは衰えることがないどころか、その社会や経済に対する影響は増すばかりである。
翻って、これらの活動が「おもしろいマンガ」を生み出すための影響力を持つのかについて、筆者は多少懐疑的である。上記の活動は、産業を活性化したりマンガ作品自体の保存を促進するかもしれないが、それらによって魅力ある作品ができるかどうかは別の話なのである。たとえば関連の博物館や大学を作ることによって、これからの漫画家たちの育成につながる、というような論は、簡単に覆すことができる。というのも、これまで世界を席巻した数々の作品は、上記のような施設がない中で生まれたのであるから、大学や博物館の設置と「優れた作家の育成」には、因果関係を確立することが本来難しいはずだ。それよりも、手塚治虫にならって世界名作童話を片っ端から読ませたり、藤子A/F不二雄にならって365日映画館に通える無料チケットを配ったり、松本零士にならって貧乏暮らしの中でミカン箱を机にさせたりした方が、作家の良い成長につながるという可能性も捨てきれないではないか。
もちろん筆者は、上記のような社会的な動きと素晴らしいマンガ作品の誕生が、まったく無関係であると思っているわけではない。特に、いつでも気軽に漫画や小説が読める施設は、マンガに出会い表現を蓄積するために小さくない影響があると予想している。しかし、たとえば小説ならば、大学や博物館の有無と関係なく、世界中で優れた作品が生み出され続けていることとおもうと、特に物語制作と社会インフラは、ほとんど関係がないような気がしてくる。
このような疑問が解決してないのは、そもそも優れたマンガ作品がどのように生まれるのか明らかにされていない(あるいは興味が持たれてない)という点にある。にもかかわらず、施設を作ることや企画をおこなうことが優先されている現状がある。マンガを描くのはある個人や集団であり、マンガイベントそのものが新しい作品を生み出すわけではないはずだ。この乖離は、マンガの内容自体や、マンガを描く、マンガを売る人、展示する人、といったそこに関わる当事者が、どのような存在なのか興味が持たれなかったことと関連している。
マンガ・アニメは一大産業であるが、物語の内容自体に興味を持つことは「オタク的」であり、数字にのみ注目することがスマートであるかのような“空気を感じる”ことが多々ある。もしピケティの展示ならば、美術館関係者がピケティに詳しいことは賞賛されることであるが、マンガに関しては「私は作品は全部読んでないんですがね」と未読であることのほうが社会人としてスマートであるかのような振る舞いに捉えられることがある。すなわちこれこそマンガ・アニメがサブカルチャーであるとされる所以であろう。「マンガは数字を持っている」ことは確かだが、一方でその数字への期待がひとり歩きし、創作の場を置き去りにしてはいないだろうか。
このことについて掘り下げるために、以下では台灣の国家漫画博物館(國家漫畫博物館)のオープニング記念式典のレポートを書いてみたいとおもう。これによって、行政がマンガを扱っている現場についてのひとつの事例として「展示すること」を考えてみたい。
“マンガを展示する”台灣国家漫画博物館
筆者は、台湾の台南應用科技大學のマンガ学科において教員として勤めている。その都合上、台湾や日本のマンガやアニメに関する情報を得やすい立場におり、自分や学生たちを取り巻く環境を含めて、マンガ文化の動向について考える機会が多いのである。
2023年12月23日に、台灣台中市で国家漫画博物館がオープンした。これまで台灣には、漫画図書館、そしてマンガ情報発信基地であるマンガBASE(漫畫基地)はあった。しかし、台灣のマンガ文化のさらなる発展のために、マンガ博物館が必要だという言説をたびたび耳にすることがあった。
そうしたなか台中市での設立が決定したという報告を、オープンわずか半年前の2023年4月に聞くことになった。私はそれを台南市の国立歴史博物館の方々から聞いたのだが、そのとき居合わせた外部の関係者は、その瞬間まで台南市に建設されると思っていたと驚いていた。実際に完成した施設は台中にあった日本統治時代の刑務所を再利用している。古い建物を観光施設や文化施設としてリノベーションするのは台灣でよくみられるまちづくりの手法である。明治大正時代の施設を、補修期間を含めて8ヶ月程度でオープンまでこぎつけた手腕は、さすが台灣というほかない。この博物館は、これから時間をかけて順次設備が増えていく予定であるという。
旧来の博物館のイメージとは異なり、街中にある気持ちのいい公園のような空間に和式の平屋が点在しており、それぞれで展示やイベントが行われる。見た目にもフラットな、風通しの良い施設である。当日の開会式で繰り返されたスローガンは「本当に来たよ!(真的來了!)」であり、ここまでに紆余曲折があったことが推察される。オープン記念式典には、文化局や台中市政の政治家たちがかけつけ、新聞報道されていた。彼らは選挙を控えているのだ、と現場の人々はあけすけに説明してくれた。
もちろん「本当に来た」とわざわざ言う理由は、政治的に振り回されて時間がかかった、という理由だけではないだろう。当然ながらマンガの持つ価値と魅力が認められ、そしてその価値へ多くの人がアクセスしやすくなることに対する台灣市民の感激を表すための「本当に来た!」の意味もあるはずだ。
マンガの価値や意味、そして解釈
では、マンガというひとつの表現ジャンルについて、一体どんな価値が、彼ら台灣の人々の心を掴んでいるというのだろうか。表現か内容か、感情や論理か。純情やバイオレンスか。オープン記念式典には、京都国際マンガミュージアムから勝島啓介事務局長、北九州市漫画ミュージアムから田中時彦館長が来賓として出席していた。台灣文化局は、博物館建設にあたって、海外はもとより、特に日本における漫画博物館の運営を参考にしたはずである。
日帝時代の建物だけではなく、展示の内容を見てみれば、そこかしこに日本の影響を感じることになる。「ジャンプ」や「マガジン」、「なかよし」といった日本の有名雑誌・人気作品の翻訳版が展示されており、雑誌だけであれば台灣マンガよりも閉める面積がずっと大きい。ちばてつやや里中真知子の挨拶ムービーが流され、いのまたむつみのイラスト原画が手に届くところに飾られている。私たちはアメリカンコミックやバンド・デシネの大きな存在をよく理解しているものの、台灣の漫画業界に限っては、日本からの輸入作品が大きな影響力を持つといっていいだろう。「ドラえもん」や「スラムダンク」といった人気マンガの海賊版がわざわざ展示されているのは、違法ながらも台灣のマンガに歴史的に影響してきた物品として広く認知されているからである。それらの無数の日本マンガ作品と、それらに対するファンの情熱が伝わってくる。
日本のマンガ作品を原文のまま読み、また展示作品をよく知っている私のような日本人からすれば、これらの作品が大々的に受け入れられ(さらには厳選して博物館に飾られることによってある種の権威付けが意図せずともなされることについて複雑さを感じつつ)、嬉しさよりは不思議さのほうがずっと強く喚起されてくる。台灣の人々は、本当にこの作品を面白いと思っているのだろうか、面白いと思っているポイントは本当に同じだろうか……?読者が作品に対して抱く「面白さ」は、つまりは解釈であり、たとえ日本人同士でも同じかどうかはわからない。私は台湾に認められた日本のマンガを前に、この素朴な疑問を抱かずにいられない。
意味の読み取りに個人差があることは前提として、もっと大きな集団としての台灣の読者たちの「読み」の中央値的な解釈はきっとあるだろうし、それと日本人読者の中央値がまったく一致するわけではないだろうと推測はするのだが、それらを証明することはなかなか難しそうである。この仮説の強化材料として提示できるものがあるとすれば、それは台灣の人たちが描いたマンガであろう。「描き」は「読み」を経てなされるので、日本漫画をたくさん読んでいる台灣の人が、どのようにマンガを描くかによって、日本漫画から何を受け取っているのかを間接的に理解できるかもしれない。
たとえばオノマトペ
台灣と日本のマンガの違いで気づきやすい要素のひとつはオノマトペである。漫畫博物館のオープン記念と同時になされた展示のなかには、台灣作家「鐡柱」氏の複製原画展もあった。彼の作品「金甲玫瑰」には、北京語と日本語のオノマトペが混在している。北京語、すなわち漢字はそれそのものが意味を持つことになり、それは音に優先する場合がある。例えばキャラクターが何かを蹴るシーンがあれば、日本であれば「ドカッ」とか「バキッ」などが描かれるところだが、北京語であれば「蹴!」(cu)と描かれる。観客の歓声の場面に「呼ー!」(hu)と大文字で描かれたりする。これらはキャラクターの行動が説明されることになるため、画面で何が起こっているのかの説明的な役割も果たす。
一方で鐡柱氏の原稿の中には、たとえば水に浮かぶ場面で「プタプタ」とカタカナで描いてある場面があり目を引く。鐡柱氏によると、「これは音だ、台灣人もわかる」という。他にも、ボクシング的競技で顔面を殴るときに「ポ」、「フア、、」と描いてある。日本だったら「フア」だと柔らかいものに当たった音と受け取られてしまうため、編集者に注意されるだろう。他にも殴った場面の「ピャ」はギリギリ変化球のオノマトペとして通用するかもしれない……などと考えているうちに、日本マンガのオノマトペにはやはり確固としたルールがあり、同時にこんなにも簡単にはずれてしまえるということに気付かされる。
鐡柱氏のカタカナは、日本人が捉えるようなオノマトペの役割と多少異なる。それは特定の音の記号というよりは、太字のカタカナが画面に書いてあることで、日本の漫画らしさを演出する働きをする記号でもある。鐡柱氏が言うからには多分それは概念として音なのだろうが、それは日本人とは異なる響きや意味合いの音のはずである。マンガという世界のなかだけで通用する、目で聞く音である。そのカタカナは、日本人には不自然だが、台灣では目で見て自然に聞こえてくる音となりうる。
スタイルの伝達と変化
こうして、少なくとも日本で生まれたマンガ作品の表現が、台灣の地で多少なりとも取り入れられ、新たな表現へと変化し続けていると記述しても、間違いはないようにおもう。それは個人のミクロな活動にも、台灣全体のマクロな活動にも当てはまる。多くの台灣作家が、日本のマンガやアニメを鑑賞し、自分の表現に取り入れている。台灣の最も有名なマンガ賞「金漫奨」の受賞作品には、日本のマンガの面影が随所に見られる。そして同時に台灣のマンガ関係者は「もっと台灣らしいマンガ」を求めている。
台灣らしいマンガ、とはなんだろうか。個別の漫画作品はそれぞれ異なる表現をそなえているはずだ。にもかかわらず「台灣」風や「日本」風とでもいうべきマクロな雰囲気を感じ取ることができるのは不思議なことである。そしてそれは私だけではなく、日本のマンガをたくさん読んできた無数の読者たちも同様であろうとおもう。つまり、台灣のマンガと日本のマンガを、作風から見分けることができるのである。ここでは、あえてそのスタイルの違いを「文体」と呼びたい。台灣のマンガ描画の文体と、日本の文体は異なるのである。ただし、台灣のマンガと香港の漫画の文体の違いはわからないため、結局自分には日本の文体かそうでないか、ということくらいしかわからないのだろうとおもう。
このような文体に違いがでること自体は驚くに当たらない。インターネットが発達しているとはいえ、言語や流通の区分から、地域差が出てくるのは当然である。台灣内であれば日本からの表現がさらに洗練され、定着していくことも考えられる。また、台灣に伝わらない日本の作品も当然あるわけで、それは日本でマンガを読み書きする人々のなかでさらに練られていくかもしれない。
さらには映画や小説、社会的現象などなど、台灣と日本の環境が持つその他無数の要因によって、マンガ表現は地域化していくだろう。いわば方言のように、マンガ表現に地域差が出てくる。現に、年代によって絵が変わるし(いわゆる絵が古いといわれる年代依存のスタイル)、雑誌を変えるだけで絵や漫画のリズム(文体)が変わってくること(いわゆる少女漫画風の絵、といったジャンル依存のスタイル)を考えると、国を隔てれば表現が変わることは当然ともいえる。むしろ国を隔てているのに、文体ともいうべき些細な違いしか生じていない、という点で、マンガ表現は特異な位置付けにある。
様々なアクター
以上のように、筆者は博物館や美術館を訪れたことで、マンガについて新しい研究的洞察を得た。筆者にとっては大変ありがたい存在である。しかしそれはやはり、マンガ研究の促進の部類の気づきを得たのにすぎないのであって、他の作家たちにとって次の創作を直接的に生み出す原動力にはなっていないのである。博物館の展示は、ある種の新たな成果物である。もちろんそれらがマンガ文化を豊かにし、周り回ってマンガ文化の成立に繋がっていくのだというのであれば、人類学的には、まずはそれらを担っている個別のアクターたちの現場をひとつの事例としてより真剣に見つめる必要がある。
博物館の展開を含めて、現代では日本のマンガやアニメがかなりカジュアルに、一般的なものとして受け入れられ始めている。それにともなって、マンガに関係する諸所のアクターたちも多様になっている。かつては、作者と読者、編集者、そして出版社と印刷所、読者と本屋さん、くらいだったマンガ関係者は、翻訳者・海外出版社・司書・大学教員・学芸員・行政担当者などなど、急速に膨らんできた。マンガを活用するNPOや市民活動、そして行政活動があるなどということは、かつては考えられなかっただろう。一方で、商業主義とは距離を置き、同人誌活動というごく個人的な創作出版活動を楽しんでいる人々も、日本には大勢いる。そのような人々で、日本のマンガ文化はできている。
この特集では、上記のような観点から、社会的影響力を持つ活動のなかでもより創作の現場に近い距離で、マンガ文化に関わっている人々をアクターとして位置付け、現代マンガの新しい局面を描き出すことを試みたい。今回は各分野の関係者に寄稿していただいた。これによって、現代のマンガ文化がどのように展開されているのか、そしてそれらによって、膨大なマンガの世界の深淵さを、明らかにするための一助となれば幸いである。
大津留香織(おおつるかおり)
人類学者、漫画家、イラストレーター。
台南応用科技大学助理教授。博士(学術)。バヌアツ共和国にてフィールドワーク調査、法と人類学の葛藤解決研究に共感と物語の研究を取り入れる。近年は漫画表現を中心としたメディア研究に取り組む。研究のかたわら創作活動を続ける。主著に『関係修復の人類学』(2020)、『人権漫画の描き方』(2024)。